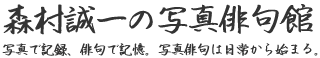第610週 写文俳句12月その2
何年か前の大晦日の夜、私は一人で六本木の街を歩いていた。なぜ一人になってしまったのか、よくおぼえていない。交差点の近くで突然、若い女性に呼び止められた。彼女は私に時間を聞いた。腕時計を見て答えると、なんと彼女も時計を腕にはめているではないか。
「故障しちゃって……」
私の視線に気づいた彼女は、少し恥ずかしそうに笑った。そして、
「少し、お時間ございません?」
と問いかけた。私は咄嗟にプロの女性かとおもったが、清楚な面立ちの、六本木にしては抑えたスーツを着ている。年齢は二十代前半、一見、OLのようである。私の好みのタイプの女性であった。大晦日の夜、一人侘しく歩いていた男にとって、棚からぼた餅のような申し出であったが、そんなオファーを受けた経験のない私は、
「あいにく、急いでいるので」
と心にもないことを言ってしまった。大都会で未知の人は敵性と見たほうが無難である。他人を信じなければ一日たりとも生きられない都会で、人があまりにも多く集まりすぎたために、人間不信のシステムと警戒心が発達したのは悲しい。
彼女のオファーを断ってから、私は男として、作家として、千載一遇の機会を逸したような気がした。引き返して彼女の姿を探したが、大晦日、六本木の雑踏の中に彼女はすでに紛れ込んでしまった。もしあの夜、彼女の誘いを受けていたら、どんな展開になっていたかわからない。都会、特に東京のような大都会は、未知の惑星の住人のような人たちが集まって来ている。地方ではあり得ないような出会いやチャンスが転がっていると同時に、危険も潜んでいる。危険を恐れていてはチャンスをつかめない。
私は本能的に彼女を警戒したが、もしかしたら、彼女も東京の一人ぼっちの大晦日が寂しくて、私に声をかけたのかもしれない。
年の瀬や独り紅白耐えられず

初出:2009年12月梅家族(梅研究会)