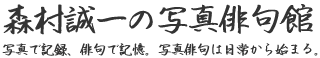第621週 写文俳句3月その2
星の陣探れる奥に恋の消え

若ければ若いほど視線は未来を向いていて、過去を顧みない。加齢と共に過去を懐かしむ感傷が強くなるが、若いころの別れにはあまり感傷はない。別れ行く友と別離の涙を交わしても、別れた後はさっぱりしている。
クラス会で再会したとしても、当時の校門の別れに遡って会うことはできない。
頭では、もう二度と会えないかもしれないとわかっていながら、今日までの延長が錯覚を生むのである。
それにクラスメートは青春の仲間ではあっても、それぞれ社会の全方位に飛び立って行った後は、相互の人生にほとんど貢献しない。青春の想い出として人生の宝石にはなっても、個人的に価値があるだけで、社会にはほとんど通用しない。
若さはこれから将来、無限の可能性の中で出会うべき多くの人間やチャンスを探している。それでよいのである。
三月はこれから巣立つ若い人々にとっては、視線を無限の未知数の方角に向ける季節である。青春とは未知数の多いことである。年齢にかかわらず、気力、体力共に若く、永遠の青春をしている人も少なくないが、加齢と共に未知数が少なくなっていくことは否めない。
だが、三月という季節は老若共に未知数が増えるような気がする。それは春という季節が予感に満ちているからであろう。
季節が透明化していく秋と比べて、季節の階段を上っていく春は、万物よみがえるエネルギーに満ち、世界は活気に溢れている。その活気が未知数そのものである。
大学に進んだ私は、山登りのサークルに入った。そのサークルに一年上級の、部のアイドルであり、全学の女王がいた。男子上級生はほとんど女王のファンであった。私も遠方からほのかな好意を寄せていた。
クリスマスイブにはサークル主催のパーティーが開かれる。女王の周辺は部長以下、最上級生の幹部が固めていて、私たち新入生は足許にも近寄れない。もちろんパーティーの後、女王を自宅にエスコートする役目も部長、あるいは幹部上級生である。
だが、その夜、どうしたわけか、女王は末席にいた私をエスコート役に指名した。私は驚いて辞退したが、女王はどうしてもエスコートしろと言った。
私鉄沿線の女王の家までエスコートした私は、夢見心地であった。満天を銀砂のような星がちりばめ、地上に薄く屯した霧が青く光って見えた。私は女王の家までの道が永遠につづけばよいと願った。
初出:2008年3月梅家族(梅研究会)