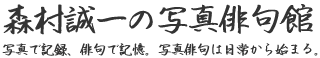第622週 写文俳句2月その3
間もなく女王の家の門前に達すると、彼女は、
「有り難う」
と言って、手を差し伸べた。私は感激して女王の手を握り返した。いまにして、その手を引けば、どんな展開になったかと惜しまれる。だが、それは後の知恵であり、当時の私にはおもいも及ばなかった。
卒業後、私はホテルに就職して、大阪に赴任した。女王は結婚してご夫君の転勤に伴い、移転した。たまたまあるきっかけから、彼女の嫁ぎ先と私の就職に伴う居所が近いことを知った。連絡を取り合い、日曜日、彼女の新居に招ばれた。
ご夫君はエリート銀行員で、在宅していたが、私にはなんの興味も示さなかった。いくら下級生とはいえ、休日、ご夫君がいる新居に新婚の奥さんを訪ねて行くのは尋常ではない。
ご夫君が在宅している女王の新居で、愉しく?数時間過ごした後、辞去した。彼女は最寄り駅まで私を送ってきてくれた。途上、私は、
「先輩、幸せですか」
と愚かな質問を発した。
「幸せとか、不幸とかは考えないことにしているわ」
と彼女は答えた。それは幸せではないという答えと同じであった。
駅で女王と別れた後、彼女の寂しげな後ろ姿が私の瞼裏にいつまでも刻まれていた。
その後、転勤の多いご夫君の後をついて移転され、疎遠になってしまった。数年後、彼女の訃報を聞いた。
女王は私を新居に招んでくれたとき、すでに自分の運命を予感していたような気がした。
おもい返せば、彼女に最後に会ったのも三月であった。なんの花か、夕風に花の香りが乗り、彼女と別れた駅の空には、春特有の小豆色の残照がいつまでもたゆたっていた。
春の夢覚めやらぬまま香り立ち

初出:2008年3月梅家族(梅研究会)