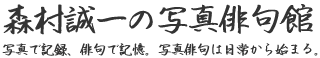第671週 写文俳句2月その4
待つ莟咲く花群(はなむら)も淡匂い

朝、行きちがって会えなくとも、下校時にチャンスがあったが、下校時はまちまちでなかなか出会えない。首尾よく時間が一致して交差点で彼女とすれちがえたとき、角の家から漂ってくる気品のある梅の香りが、彼女の残り香のように感じられた。
梅の香る早春に、一瞬の交差点で彼女とすれちがう頻度が高くなるような気がした。おそらくは先方になんの印象も止どめなかったであろう一方的な出会いであったが、梅の香りは私の初恋を包む香りであった。
ただ一言の言葉を交わしたわけでもなく、ほんの数秒、梅の香る街角での出会いが、その後の私の異性に対する宗教的な憧憬の原点になっている。
その後、馬齢を重ねて人並みに憂き世の汚濁に染まっても、早春の寒気に凛として立つ枝振りと、気品ある清らかな香りは、私の初恋の面影の残り香のようになっている。
桜や椿や他の花では、いくつかの恋と重なることはあっても、初恋の面影の人とは重ならない。名前も住所も知らぬ郷里の街角ですれちがっただけの幻の少女は、いまでも私の青春の記憶の中で、梅の花とオーバーラップして不動の位置を占めている。
他の花をもっては替え難い幻影が、あたかも梅の花精であったかのごとく、私の追憶の中で永遠なのは、ついに達することのなかった初恋こそが、梅のように清らかな形と、気品ある香りを不朽のものとしているからであろう。
恋は達成した瞬間に、恋そのものを恋するストイックな姿勢を失う。あたかも花精に恋するがごとく、想いを捧げることはできても、それに触れてはならない。ストイックな純愛こそが初恋であり、それゆえに永遠の香気を失わないのである。初恋を季節化したのは二月であるかもしれない。
初出:2010年2月梅家族(梅研究会)