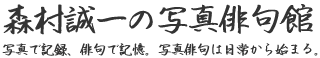第644週 写文俳句8月その3
三日ほどして、ようやく余燼(よじん)がおさまり、焼け跡に入って後片付けができるようになった。私も父を手伝って焼け跡に入った。隣家との境の路地に、私たちがこの間、飢えをつないだ裏庭のかぼちゃが落ちていた。なぜ、かぼちゃがこんなところに落ちているのかと不審におもいながら取り上げようとした私は、ぎょっとなって後退(あとじさ)った。焼けたかぼちゃと見えたのは、胴から離断した人間の頭部であった。
逃げ後れ、路地に迷い込んだ人が焼夷弾の直撃でも受けたのであろう。その人の身元はついにわからなかったらしい。
私は星川を埋めた死体と、焼けたかぼちゃのような人間の頭部を自分の目で見たとき、いつかこの光景を書きたいとおもった。
市内の焼け跡には焼け棒杭で組み立てた掘っ建て小屋(バラック)が建つようになり、夜になるとまばらな電灯がついた。それは私にとって新鮮な驚きであった。もう灯火管制も空襲もない。夜になっても好きな本を好きなだけ読める。灯火は夜毎増殖して、一望の廃墟にその密度が濃くなっていく。
現在、人工衛星から見下ろした日本列島は光の帯となっている。当時、焼け跡に散らばった灯火は、平和回復の象徴であった。
私は夏になると、いつもあの空襲の夜と、廃墟に散開した灯火をおもいだす。
特攻に出撃した若者を見送った基地の町の女学生の腹には、二人の愛の結晶が芽生えていた。女学生の「生きて還(かえ)って」という切なる願いも虚しく、飛び立った若者は還って来なかった。それから間もなく戦争は終わり、女学生は子供を産んだ。母一人子一人の生活の中で、生まれた子はすくすくと成長していった。父の形見は、母と共に過ごした短い時間の中に差し向かいの食事を摂った箸一膳であった。
青いはし使われるのを待ちながら父のいない思春期は過ぐ
(森村冬子)

初出:2008年8月梅家族(梅研究会)