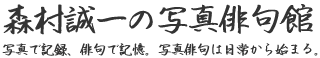第687週 写文俳句6月その3
かりそめの面影と知れ傘の内

雨中に置き忘れたような想い出は私にもある。学生時代、といっても留年して、さしたる講義もなく閑(ひま)をもてあましていた私は、一人で北陸地方をまわり、富山から高山、名古屋を経て、吉野の熊野古道を伝い、新宮、潮岬へ抜ける旅行をした。
途上、富山駅でベンチに腰掛け時間待ちをしていた私は、ぼんやりと自分の将来を模索していた。留年は態のいいモラトリアムであり、私は社会に押し出されるのが怖かった。自分には生活能力があるのかないのか、果たして社会に出て自立していけるのか。過剰な自信は一人旅をしている間に、空気が抜ける風船のように萎んでいった。少なくとも学校に草鞋(わらじ)を預けている間は、学生として社会の荒波にさらされることはない。
六月の下旬で雨が降っていた。駅の同じベンチに少し距離をおいて若い女の子が坐っていた。彼女も一人旅らしく、スーツケースを持っていた。私はなんとなく彼女が気になっていた。同じホームの同じベンチに腰掛けているので、同じ方角に行くのだろうとおもったのである。
初出:2010年6月梅家族(梅研究会)